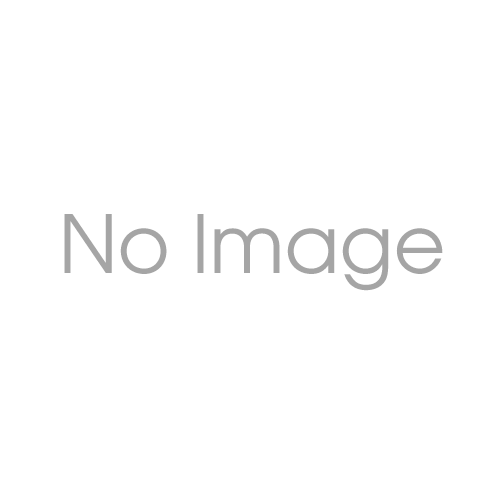2020年の外出自粛期間をきっかけに、フードデリバリーの需要は急速に拡大しました。その後も、共働きや単身世帯の増加に伴い、需要はさらに高まり続けています。
今後さらに成長を続けるフードデリバリー市場において、売上拡大を目指して参入を検討している飲食店も少なくありません。現在はデリバリーの注文経路も多様化しており、その仕組みや特徴を十分に理解できていない店舗も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、多様化するフードデリバリーの注文経路とそれぞれのメリット・デメリット、成功させるポイントを解説します。この記事を読み終える頃には、フードデリバリーを活用して販路を拡大し、売上向上を実現するための具体的な対応策を得られるでしょう。
デリバリー専門店のあらゆる課題を解決!
デリバリー専門店向けオーダーシステム
リピーター獲得とデリバリーの効率化を同時に実現!
飲食店向けのデリバリー・テイクアウト専用スマホアプリ
フードデリバリーとは?
フードデリバリーとは、飲食店で調理した料理をお客様の自宅やオフィスなど指定の場所まで配達するサービスを指します。フードデリバリーは「出前」とも呼ばれており、江戸時代から利用されているサービスです。
デリバリーは元々、飲食スペースを設けていない配達に特化した店舗で使用されていました。昨今はコロナ禍による巣ごもり需要の増加により、さらに勢いを伸ばしています。
多様化するフードデリバリーの注文経路|メリット・デメリット

現在のフードデリバリーの注文経路は多岐にわたります。具体的な注文経路とメリット・デメリットは下表のとおりです。
|
注文経路 |
配達方法 |
メリット |
デメリット |
|
電話注文 |
自社配達 |
手数料がかからないため利益率が高い。高齢者が利用しやすい |
人件費や電話応対にコストがかかる |
|
来店注文 |
自社配達 |
手数料0で利益が残る。高齢者も利用しやすい |
接客に時間を取られる |
|
Web・アプリ注文 |
【自社配達】フードデリバリーサービス |
販促費や配達手数料を抑えられる |
注文から配達までの時間管理が必要 |
|
【配達代行】フードデリバリーサービス |
配達業務を効率化できる。販促活動が不要になる |
1件あたり30〜45%程度の手数料が発生 |
|
|
【自社配達】自社注文サイト・アプリ |
費用が月額固定なので利益を出しやすい |
販促活動を自社で行う必要がある |
|
|
【配達代行】自社注文サイト・アプリ |
配達代行費用が比較的低価格で設定されている |
配達員不足が発生する可能性がある |
上表のとおり、どの注文経路にもメリット・デメリットがあるため、さまざまな注文方法に対応することが売上拡大には重要です。ここでは、各注文経路の特徴とメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
電話注文
お客様が注文チラシに記載された電話番号から、直接店舗に注文する方法です。昔からある方法で、30代以降の人には馴染みがあるのではないでしょうか。
電話注文の良いところは、配達を自社で行うため、配達手数料などがかからず利益率が高い点です。また、スマホやPC操作が苦手な高齢者にも適しています。
一方で、注文の記録や管理が手作業になる点や、販促用チラシの印刷費用、ポスティングにかかる人件費が発生する点はデメリットです。
来店注文
お客様が店舗に直接来店し、注文内容と予約日時を伝えてデリバリーを注文する方法です。注文してその場で受け取るテイクアウトも含まれています。
来店注文のメリットは、お客様がメニューを実際に確認し、店舗の雰囲気を体験できることです。店舗の雰囲気を気に入ってもらえれば、リピーター獲得にもつながります。また、自社配達なので、手数料が発生せず利益率が高い点もメリットです。
ただし、来店時の注文業務で接客に時間を取られる点はデメリットといえます。顧客満足度を維持するために、最適なオペレーションが求められるでしょう。
Web・アプリ注文
近年主流になりつつあるWeb・アプリ注文は、お客様がWebサイトやアプリから料理を注文する方法です。「フードデリバリーサービス」と「自社ECサイト・アプリ構築」の注文経路に分かれます。
それぞれの特徴とメリット・デメリットを見ていきましょう。
フードデリバリーサービス
フードデリバリーサービスとは、お客様のPCやスマホを通じてプラットフォーム事業者が注文を受け付け、配達するサービスです。
代表的なサービスには、
- 出前館
- Uber Eats
- Wolt
- menu
などが挙げられます。また、フードデリバリーサービスにも、「自社配達」と「配達代行」の2種類があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットは以下のとおりです。
【自社配達】
注文プラットフォームは出前館・Uber Eatsなどのフードデリバリーサービスを利用し、店舗の従業員が配達を行う方法です。
プラットフォームに掲載するだけで注文が入るため、販促費を抑えつつ収益を上げられます。また、自社配達によって配達手数料も10〜15%ほど抑えられます。
ただし、配達スタッフの採用や管理、オペレーションの構築などが必要な点はデメリットです。
【配達代行】
注文プラットフォームはフードデリバリーサービスを利用し、配達業務も同サービスの配達員に委託する方法です。
配達代行を行っている主なフードデリバリーサービスには、出前館・Uber Eats・Wolt・menuが挙げられます。
プラットフォームに店舗情報を掲載するだけで注文受付・配達を行ってくれるため、注文をさばきやすい点がメリットです。
一方で、1件あたり30〜45%程度の手数料がかかるため、利益率は低下します。
また、配達員の質が委託先に依存するため、顧客満足度をコントロールしにくい点も欠点です。
自社ECサイト・アプリ構築
前述した出前館やUber Eatsなどのフードデリバリーサービス以外にも、自社ECサイト・アプリを構築する方法もあります。ECサイトやアプリの制作会社に開発依頼するのが一般的です。
自社ECサイト・アプリを構築する方法には、自社配達と配達代行の2パターンがあるので、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
【自社配達】
自社でECサイトやアプリを構築し、配達も自前で行う方法です。
自社配達型の自社注文サイトのメリットは、フードデリバリーサービスや配達員を利用しない分、手数料が発生しない点です。サーバーまたはシステム利用料が月額固定の場合が多いため、利益も出しやすくなります。
ただし、販促活動を自社で行う必要があり、それには集客の知識や経験が必要です。自社にマーケティングの知識に精通している人材がいなければ、売り上げが伸びない期間があるでしょう。
【配達代行】
自社で注文サイト・アプリを構築し、配達員は「UBER DIRECT」や「Wolt Drive」の外部サービスと連携してデリバリーする方法です。
自社配達に比べてスタッフの雇用や管理負担を軽減できます。また、配達代行費用も比較的安価に設定されているため、費用面でも大きな負担にはなりません。
一方で、配達員は「UBER DIRECT」や「Wolt Drive」に全て任せるため、地域や時間、天候によっては人員が足らず、デリバリーできないことがあります。
フードデリバリーを成功させる5つのポイント
飲食店の売り上げを伸ばすためには、多様化するフードデリバリーの注文経路に対応することが大切です。しかし、ただフードデリバリーサービスを利用するだけでは、なかなか成功には結びつきません。
ここでは、フードデリバリーを成功させる5つのポイントを解説します。
さまざまな注文経路に対応する
フードデリバリーの成功には、多様化する注文経路への対応が欠かせません。
注文経路とは、
- 電話注文
- 来店注文
- Web・アプリ注文
のことです。それぞれの注文経路には、異なる客層や利用状況があります。
たとえば、高齢者であれば電話注文が利用しやすい一方で、若者世代にはアプリやWeb注文が主流です。
このように、どちらかを選択するのではなく、さまざまな注文経路に対応することで、幅広い客層にアプローチできます。
結果として新規顧客・リピーターの獲得につながり、売上アップが期待できるでしょう。
SNSで発信する

フードデリバリーの集客においてSNSは強力なツールです。成功している飲食店は、XやInstagram、TikTokなどをうまく活用しています。
SNSは幅広い層が利用しているため、新規顧客の獲得に役立ちます。発信内容としては、メニュー紹介やキャンペーン情報、店舗のこだわりなどを伝えるとよいでしょう。
ただし、不適切な投稿やコミュニケーションを行うと、炎上につながる点は注意が必要です。
SNS運用は大きな効果が期待できる一方でリスクもあるため、慎重な運用を心がけましょう。
Googleマイビジネス(MEO)を活用する
地元のお客様にフードデリバリーを認知してもらうために、Googleマイビジネス(MEO)を活用するのもおすすめです。
Googleマイビジネスは、Google検索やGoogleマップなどに、店舗情報を表示できるツールです。
Google検索やマップで店舗が上位表示されるよう最適化を行えば、検索結果に自店舗の情報が表示される機会が増えます。
営業時間、メニュー、口コミ、写真などの情報を充実させることで、注文につながりやすくなります。
顧客満足度の向上に徹底的にこだわる
フードデリバリーの成功には、顧客満足度の向上が重要な要素のひとつです。料理の品質はもちろんこと、注文から配達までをスムーズに提供することも大切です。
他にも顧客満足度の向上にこだわる方法として、
- レシートに「ご注文ありがとうございます」などの感謝のメッセージを印字する
- 問い合わせ窓口の設置
- 配達員の接客態度の見直し
- 配達時間の速さ
- 一番美味しい料理の温度
などが挙げられます。顧客満足度の高い飲食店は、リピーターの増加につながります。
お客様からのフィードバックを積極的に取り入れ、サービス向上のために迅速に対応する姿勢が大切です。
分析と改善を愚直に続ける
データ分析と改善を継続的に実践することは、フードデリバリーの成功には欠かせません。
売上データや注文数から人気メニューの把握、配達エリアの動向など、収集したデータをもとに改善点を明確にすることが大切です。
たとえば、人気のないメニューは改良または削除する対応や、Webサイト・アプリのメニュー写真の改善などできるところから始めてみましょう。
小さな改善の積み重ねが、全体的なサービス品質の向上と顧客満足度の向上につながります。
フードデリバリーをスタートする際の課題

ここでは、多くの飲食店がフードデリバリー開始時に直面する3つの課題について解説します。
複数ある注文経路の管理が大変
本記事では一貫して、さまざまな注文経路に対応することがフードデリバリーの成功には欠かせないとお伝えしてきました。
しかし、複数ある注文経路に対応する場合、電話注文、来店注文、Web・アプリ注文などを同時に管理する必要があります。
そのため、人員を増やすためのコストがかかり、人員が少ない店舗では従業員への負担が大きくなるでしょう。
配達効率の課題
料理の配達を自社スタッフで行う場合、配達効率の課題があります。
ノウハウが蓄積されていない店舗では、配達スタッフのスケジュール管理やルート設定の効率化ができていないことがほとんどです。
その結果、配達の遅延や無駄な移動が発生する可能性があります。配達員の管理機能や配達を効率化する機能を備えたツールの導入がおすすめです。
注文手数料による利益率の低下
フードデリバリーサービスを利用すると、プラットフォームに支払う「注文手数料」が発生します。
注文件数が増える点はメリットですが、その分店舗の利益に影響し、結果として利益率が下がってしまう可能性があるのです。
また、利益率を上げるために商品の価格を引き上げると、顧客離れを招くリスクもあります。この課題を解決するためには、注文単位で注文手数料が発生しない「自社Webサイト・アプリ」の構築がおすすめです。
デリバリーサービスの課題を解決する「宅配Evolution」「くるリピ」の導入がおすすめ

前述したとおり、デリバリーサービスには
- 複数ある注文経路の管理が大変
- 配達効率の課題
- 注文手数料による利益率の低下
といった課題があります。多くの飲食店が抱えるこれらの課題を解決するのが、「宅配Evolution」「くるリピ」です。
ここでは、2つのサービスの特徴を解説します。
デリバリー専門店のあらゆる課題を解決する「宅配Evolution」
「宅配Evolution」は、「電話注文」「来店注文」「Web・アプリ注文」の3つの注文経路を一元管理できるデリバリー専門店向けオーダーシステムです。クラウドシステムのため、PCやタブレットからいつでもどこでもアクセスできます。
宅配Evolutionには、デリバリー専門店を運営するために必要な機能を備えています。具体的な機能は以下のとおりです。
複数の注文経路の一元管理
「宅配Evolution」では、電話注文、来店注文、出前館やUber Eatsなどのフードデリバリーサービス、自社Webサイトやアプリでのネット注文といった複数の注文経路を一元管理できます。
また、複数のフードデリバリーサービスを利用する際は、各社に専用タブレットを設置する必要がありますが、宅配Evolutionはその必要がありません。
ひとつのタブレットで注文や売上データの一元管理が可能です。(「Uber Eats」「出前館」「menu」「Wolt」に対応)
配達管理の最適化
宅配Evolutionには、配達時に役立つ機能を備えています。
たとえば、配達用伝票に配達先を示したQRコードが印字され、配達員がスマホで読み取るだけで、即座にナビを利用して配達ルートを確認することが可能です。
売上データの分析
「宅配Evolution」では、フードデリバリー別や注文経路別の分析が可能です。人気メニューの把握や注文数の時間帯別傾向などのデータを収集・分析できるため、簡単に改善点を明確化できます。
デリバリー専門店のあらゆる課題を解決!
デリバリー専門店向けオーダーシステム
リピーター獲得とデリバリーの効率化を同時に実現する「くるリピ」
「くるリピ」は、飲食店向けのデリバリー・テイクアウト専用スマホアプリです。販売促進・フードデリバリーサービス各社の一元管理・本部管理側の売上集計や顧客分析がひとつになっています。以下では、くるリピの特徴を3つ見ていきましょう。
注文手数料の削減
くるリピの大きな特徴とも言えるのが、注文手数料を削減できる点です。よくある自社ECサイト・アプリでは、注文単位で手数料が発生する従量課金制が多く、店舗の利益率を圧迫します。
その点くるリピは、売上に対する配達手数料や注文手数料が発生しないため、利益率アップが期待できます。
多彩なクーポン配信による販売促進
くるリピでは、期間限定の割引やセット購入での割引など、販売促進をサポートするクーポン配信が可能です。
自店舗用のお得なクーポンやニュースを作成し、お客様のスマホにプッシュ通知でお知らせすることもできます。
クーポン配信をうまく活用すれば、顧客の囲い込みにも繋げられるでしょう。
デリバリー・テイクアウト注文に特化したUI
くるリピのUIは、デリバリー・テイクアウト注文に特化しているため、お届け先の入力からメニューオーダー、注文までをスムーズに操作できます。
ゴーストレストランのような複雑なメニュー形態を提供する飲食店でも、マスタ設定だけで対応可能です。
リピーター獲得とデリバリーの効率化を同時に実現!
飲食店向けのデリバリー・テイクアウト専用スマホアプリ
まとめ|フードデリバリーサービスを活用して売上を最大化しよう
フードデリバリー市場は、共働き世帯や単身世帯の増加により需要が拡大しています。フードデリバリー業界で飲食店が成功するためには、さまざまな注文経路への対応が重要です。
注文経路には、電話注文や来店注文、Web・アプリ注文があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。簡単におさらいしていきましょう。
|
注文経路 |
配達方法 |
メリット |
デメリット |
|
電話注文 |
自社配達 |
・手数料がかからない ・高齢者が利用しやすい |
コストがかかる |
|
来店注文 |
自社配達 |
・手数料0で利益が残る ・高齢者も利用しやすい |
接客に時間を取られる |
|
Web・アプリ注文 |
【自社配達】フードデリバリーサービス |
販促費や配達手数料を抑えられる |
配達管理が必要 |
|
【配達代行】フードデリバリーサービス |
・配達業務を効率化できる ・販促活動が不要になる |
1件あたり30〜45%程度の手数料が発生 |
|
|
【自社配達】自社注文サイト・アプリ |
費用が月額固定で利益を出しやすい |
販促活動を自社で行う必要がある |
|
|
【配達代行】自社注文サイト・アプリ |
配達代行費用が低価格 |
配達員不足が発生する可能性がある |
フードデリバリーは成長著しい業界であり、飲食店がさまざまな注文経路に対応することで売上アップを狙えます。
デリバリーサービスに自社システムを構築したい飲食店様は、お気軽にお問い合わせください。
デリバリー専門店のあらゆる課題を解決!
デリバリー専門店向けオーダーシステム
リピーター獲得とデリバリーの効率化を同時に実現!
飲食店向けのデリバリー・テイクアウト専用スマホアプリ